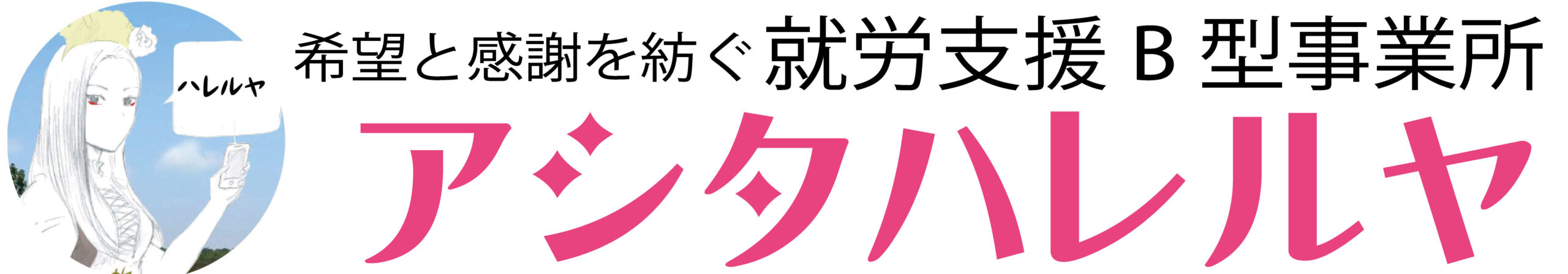目指しているもの
ある日の質問
目の見えない人にはどう対応するのですか?
ある日そのような質問をいただく機会がありました。
私の答えは「当事業所では現時点では対応できません。その人が幸せになれる環境に恵まれることを祈るだけです」
私の率直な気持ちであり、正確な判断だと思っています。
福祉の仕事は利用者の尊厳を守り、生活のリズムを整え、普通の生活を送れるよう支援することだと思います。
「普通の幸せ」はとても大事なことだと思います。それを実現するために、様々な事業所の方々が日々努力をされているのだと思います。
私は、福祉の世界では新参者であり、会社経営の経験があるという条件のみクリアしてこの世界に参入しました。
きっかけは、広告のものづくり制作を行ってきた知識と技術を提供することができると思ったことです。
これらをレクチャーすることで、就職するだけでなく、チームで、または人によっては、
単独でも収入をえることができる技術を伝えることができ、その土台となる環境を提供することができます。
提供できる環境とは当事業所独自のもので、根拠となるのは充実した設備と、本社運営での結果から証明できるものです。
そして、その知識や技術は、
・細分化することで誰でも参加できるレベルまで難易度を下げていくことができること。
・難易度を下げたことで、有名企業などの仕事を経験する機会を提供できること。
・その上で、その仕事に参加したことで利用者の自信につなげることができること。
・利用者の見えている可能性、まだ見えていない可能性につなげることができること。
以上が確実に可能となる土台があります。
実際、当事業所の利用者にはその通りの作業を提供し、学習する場と時間を提供し体感していただいています。
当事業所を選択し契約を結んだ利用者に対し、可能性につながる幸せを提供し続けるつもりです。
しかしながら、
事業所の運営というのは収益が獲得できてこそサービスが提供できるという現実があります。
運営上必要な収益を獲得することと、当事業所が目指すサービスの両立には経験という要素がかかせないと考えています。
現在は良いメンバーが集まっておりますが、収益面では明るい見通しがありますが、さらに経験を生かしたいという方と、チームワークを持って事業所の発展に繋げ、世の中に質の高いサービスを提供できればと思い応募を募っております。
実は、冒頭の質問に関する答えはもう一つあります。
当事業所の本社には点字を印刷できる設備があります。
この設備や技術を生かして、目が見えない利用者の方にタイピングを習得してもらうことが出来れば、そのデータを事業所で編集し、印刷物やシール、壁紙(壁紙に直接印刷する設備があります)、手すり、商業施設のあらゆよる場所に設置し世の中に貢献することも可能です。そのための販路づくりは本社の得意とするところです。
設備・モノ・販路・人などは十分に揃っている事業所で
自分の経験を生かしてみませんか?
民間の会社経営をしてきましたので、非効率的なことは極力しないというのがメリットです。
しかしながら、けっしてサービスに手を抜くということではありません。
数ある事業所の中で、ある側面では世の中に貢献できる強さがある事業所で一緒に発展しませんか?
就労継続支援B型事業所アシタハレルヤ
施設長 松 浦 鉄 也
転職で失敗しないために
転職で失敗しないためには、現状分析が大切です。
当事業所も運営している就労継続支援B型事業所は、ここ数年で一気に件数が増えました。
札幌でも10年前から比較すると3倍以上の件数になっています。
その理由は行政側が民間企業の参入を促したからですが、行政が新規参入を促した理由も見逃せない部分です。障がい者への理解といった部分ももちろんありますが、従来型の事業所では構造的に問題があるとみて新規参入を促し、改善を図ったとみてよいでしょう。
さて、これだけ事業所が増えたわけですが、平成27年度以降は倒産する事業所が増え始めてきました。増えている事業所の数とは裏腹に、倒産も増えていくというわけです。
これは淘汰を意味します。事業所として意味のある活動・運営をしている本物だけが残る時代になります。
運営の仕方はそれぞれですが、本気で利用者やスタッフのことを想い、
時には共に苦難を乗り越えることのできるチームや、その骨格となる
コンセプト、事業所の在り方が重要です。
新規参入でこれだけ増えた事業所は利用者の確保に躍起になり、運営が集客主体となっています。これでもかと、食事や工賃、その他、短期的に目に見えやすいメリットのオンパレードです。これではいずれ限界が訪れ撤退や倒産する事業所が増えてくるでしょう。
利用者だけではありません。
サービス管理者に対する待遇も一気に上がりました。これは需要と供給のバランスが関係しています。
従来型の事業所では内部構造や上下関係を意識するあまり、サービス管理責任者を増やすことを積極的に行いませんでしてた。サービス管理責任者を増やし知識を共有すよりも現場の人間、作業員の数の確保を意識したからです。
福祉の業界であるのに福祉の精神よりも、上下関係などの体制を維持することを意識したといえます。
本来は特別な試験もなく、経験と学ぶ心さえあれば取得できる資格ですので、より多くの人に学ぶべき場所を提供すべきでしたが、従来型の事業所ではそれを行っていませんでした。これが行政が新規参入を促した原因の一つでもあると思います。
そのため、現在は事業所の数に対しサービス管理者の数が少ない状態となり、新規参入事業者はサービス管理責任者を好待遇で招き入れるという構造が出来上がりました。
しかし実際はどうでしょうか?常に多くの転職希望者がいるのが「サービス管理責任者」の現状です。
この転職希望者には2種類のパターンがあるといえるでしょう。
1 将来を見据えての行動を検討している。
2 好待遇のところが増えたので、今の事業所はいつでもやめる事ができる。
1の方は人生設計を考える上でも重要なことだと思います。
私達はこのような方と語り、運営を盛り上げたいと思います。
2の方に関しては、雇用側もそのつもりで雇用するでしょう。
簡単にいうと「もっと良い人材をみつけたらすぐに取り換える」ということです。また、2のような方の特性として自分より優れた人材を毛嫌いします。
人にはそれぞれ優れた部分があるのでそれを生かしてチームとしてやっていこうという協調性が本人が思っているより足りていないのです。
仮にも福祉の仕事をしているのにもかかわらず。
では、2に関してそれを実証するような面接結果があります。
以下の通りです。ご確認ください。
面接事例
30代女性 サービス管理責任者
転職回数5回
転職希望理由
事業所の代表が職員と不倫して離婚。代表の出勤率が下がり現場の士気が低下。従業員が恐らく全員辞めるであろうとのこと。その後、こちらで求人内容を調査しましたが、困っている様子はなく通常営業しています。
当事業所の見解 ~
原因は誰だったのでしょうか?
40代女性 サービス管理責任者
転職回数7回
転職希望理由
立ち上げたばかりのB型事業所。入社2か月。代表は社労士でもあるのに、雇用契約がいまだに結ばれない?営業も任されているが在宅で電話営業をしている。職業指導員や生活支援員からは「営業も私たちがやりますよ」と言われている。その他本人の発言は事業所の設備については文句が多い印象でした。
当事業所の見解 ~
周りから敬遠されているのではないでしょうか?
つなぎのサビ管とされているのではないでしょうか。
50代女性 サービス管理責任者
転職回数12回
転職希望理由
グループホームでサービス管理責任者をしているが、入社時から事業所が荒れている印象があり、これは管理に問題があると判断。上司に意見したが聞き流され、さらに本社にも連絡し掛け合ったが聞き流されたとのこと。普段の業務はほぼ在宅とのこと。当事業所を面接時見学した際は、これは良いあれはダメと判断し帰られました。
当事業所の見解 ~
雇用する側は従業員への責任をもち期待して雇用します。
事業所が荒れているのであれば、サービス管理者としての力量を期待されていたのではないでしょうか。
ご本人の努力はどこにあるのでしょうか。
適切な相談であれば、事業所改善につながるなら運営者はすぐに行動に移すはずです。事業主や、管理者、上司も事業所の環境が悪い状態であることは望まないはずです。もし本人の言う通りの事業所であれば先は長くないでしょう。
要約 転職に成功するには
コンセプトを理解し、業界の現状とこれからを理解し判断する。
チームプレーができるかどうかで判断する。
経営方針を理解し、しっかり質問してから判断する。
楽しく、やりがいのある職場にいたら転職なんて思いつきません。
転職を繰り返している人を何名も面接しましたが、幸せそうには見えませんでした。
同じ失敗を繰り返しているのかもしれません。
転職は、やりがいや将来を見据えてするものです。そのやりがいも独りよがりだと、転職は成功しません。
環境改善としては給料も一つの指標ですが、チームプレーや事業所に想いをもって作業し、その一歩一歩がよりよい未来を築きます。
当事業所のスタッフはもちろんですが、当事業所の利用者もそれを信じてくれています。
環境は皆で作ることができるはずです。そのためには現状を理解し、
できることから協力して進め、確かな未来を築くしかないと思います。
就労継続支援B型事業所アシタハレルヤ
施設長 松 浦 鉄 也
当事業所と本社の実績
本社の実績を活かし、利用者と社会の懸け橋となる事業所を目指します。
本社の実績
業務 販促物制作・広告制作
実績一例 直接取引
(下請けではありません)
焼鳥の「串鳥」札幌開発㈱様
対応 : タペストリー制作
トラクターのヤンマー様
対応 : カーラッピング
ウポポイのアイヌ民族文化財団様
対応 :飛沫対策アクリル・紙芝居制作・什器製作・ステッカー制作
フードデリバリーのWolt Japan様
対応 :カーラッピング・マグネット
よさこいの新琴似天舞龍神様
対応 :ステージパネルデザイン制作 2018年より毎年協賛
老舗ゼネコンの錢高組様
対応 :新築マンションのサイン工事
その他
現役衆議院議員WEBサイト管理
不動産WEBサイト管理など
取引社数 88社
近年では海外からの問い合わせも数件発生
他の取引実績
㈱宣美 様 大丸百貨店装飾
シャチグループ様 ススキノ
㈱家物語様 脱毛エステ装飾
ススキノ野口ビル様
ふじ研究所様 ゼネコン関連
大洋ビル様 不動産サイン
アンサンブル㈱様 不動産サイン
㈱スター商事様 材料販売
㈱ブレナイ社様 道産食材コンサル
川沿脳神経外科様 カード販売
エイチアールエージェンシー様 車両マグネット
くのいちキッチン様 車両装飾
エレベーターコミニケーションズ㈱様 EV装飾
北海道民泊㈱様 サイン一式
大輝印刷㈱様 看板関連
表示灯㈱様 地下鉄関連
佐藤印刷㈱様 看板関連
㈱装研 ディスプレイ印刷
炭火焼雅咲様 キッチンカーラッピング
㈱スタイル様 印刷関連
ブルーサイン様 看板関連
㈱ink様 印刷関連
㈱北海道吉村様 材料関連
田代商会㈱様 BMW壁紙
北海道通信印刷㈱様 サイン関連
北日本警備㈱様 看板関連
シズナイロゴス様 カーラッピング
鳥よし 看板関連
ウォーターセーフティ協会 カーラッピング
東洋産業㈱ 新規店舗装飾
㈱ケーワンエンタープライズ様
U-lead様
他 数十社